『地域環境学科』への招待
平成18年4月開設の「地域環境学科」の概要
![]()
■ 環境学部 環境学部は自然との共生をテーマに、すまい環境や地域環境から自然環境に
広がる「よりよい環境づくり」を目指し、平成18年4月、2系3学科構成で新たに出発い
たします。
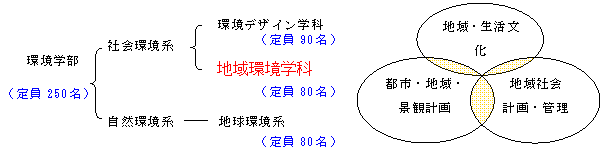
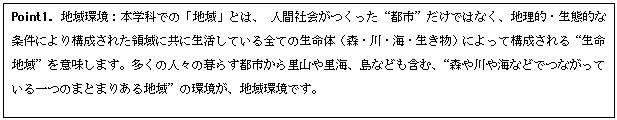
■ 地域環境学科 地域環境学科は、地域の社会環境や自然環境との対話・調和を通じて生活・
文化に根ざした地域のあり方を探求し、ハード・ソフト両面で地域の環境づくりができる専
門知識や専門技術を修得します。具体的には、図に示す3分野を、フィールドワークなどを
通して実践的・実感的に学びます。環境に配慮して地域を企画・計画・管理する能力を備え
た人材を育成するのが本学科のねらいです。
■ 地域環境学科における「学びの5つの特徴」
1. 地域環境学科は、環境デザイン学科と共に「社会環境系」という「系」を構成しています。
この系では、近接分野の学習を可能にする意味で、 1年次はこれら2学科で共通科目を学び、
2年次から学科独自の科目を学習します。
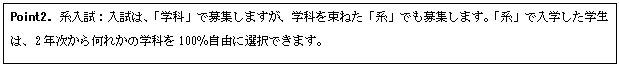
2. 地域環境学科では、社会が必要とする≪地域≫を対象として、地域の社会環境や自然環境と
調和した『まちづくり』、『コミュニティづくり』や『地域環境ネットワークづくり』等々
の“地域の環境づくり”に関する各種の専門知識・技術を実践的・実感的に学びます。
3.
そのためには、自然科学、社会科学等々の学問の複合領域について目配せし、それらをベー
スに、地域環境学科独自の教育プログラムに基づき、誰でもが、専門分野を段階的に学ぶこ
とができます。
4. 地域環境学科は、理数系・文系に興味を持つ多くの人たちが共に学ぶ、“文理融合の学びの
場”です。ですから、理数系の生徒・学生はもとより、文系の生徒・学生も十分に学ぶこと
ができます。
5. 地域環境学科の学びの方法としては、体験による発見を大切にし、そこから生まれた興味を
自発的に育てる“フィールドワーク”などを取入れた実践的な「体験型学習」を重視し、こ
れらに関する授業を数多く開講しています。
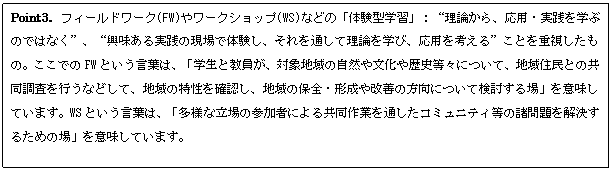
■ 地域環境学科の3分野とその学習内容 地域環境学科では、3つの分野から地域のあり方を探っていきます。
|
分野 |
関連授業科目 |
学習内容 |
|
都市・地域 ・景観計画 |
都市計画、地域環境の企画、地域・地区の計画など |
私たちが活動している場である都市・地域の環境整備について学びます。 |
|
植栽と造園計画、景観計画、ランドスケープ演習など |
建物等人工物と自然環境が調和した地域の空間や景観の整備・形成について学びます。 |
|
|
地域社会画 ・管理 |
まちづくり計画、まちづくりプロジェクトなど |
住民主体の個性的かつ潤いのあるまちづくりについて学びます。 |
|
地域環境政策、地域環境管理、環境政策・管理演習など |
自然環境を保全・再生し、地域社会を維持させていくための環境政策や管理の方策について学びます。 |
|
|
地域・生活文化 |
地域・生活文化、地域・生活文化演習など |
地域の生活文化(衣・食・住、暮らしや祭りなど)について学びます。 |
|
地域環境社会学、環境社会学演習など |
地域が持つ社会のしくみから社会環境のあり方を探っていきます。 |
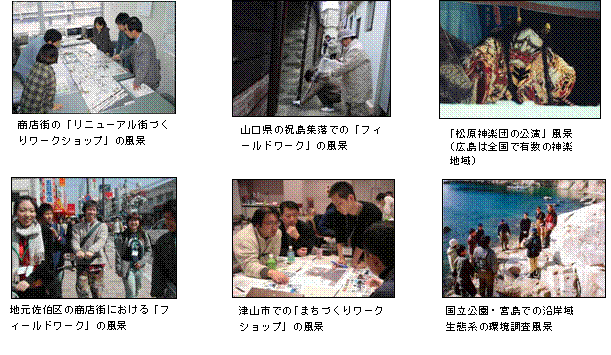
■ 学科の各分野の具体的な活動事例 ・山口県祝島集落での“いえ”づくりと“まち”づくり ・ ・公営住宅の再生計画と“まち”づくり ・医療並びに高齢者施設等の施設配置計画 ・市町村合併した町の“まち”づくりと“景観”づくり ・瀬戸内海国立公園の環境診断カルテづくりと 環境管理 ・ ・ ・宮島の市民参加型のまちづくり ・中国の長江流域の民間祭祀 ・大竹まち学び・まちづくり学校 ・建物を含めた地形図の3次元CGの生成 ・地域アメニティの形成と地域再生 ・その他
■ めざせる主な資格 教育職員免許状高等学校教諭一種免許状(工業)、 土地家屋調査士、 宅地建物取引主任者、 技術士補(試験科目の一部免除)、 2級建築士、 木造建築士(実務経験1年)、 1・2級建築施工管理技士、 1・2級造園施工管理技士、 環境プランナー、 再開発プランナー、 マンション管理士、 消費生活アドバイザー ■ 卒業後の主な進路
卒業生の活躍が期待される分野としては、都市計画・建設関連のコンサルタント業、 建設業、 住宅メーカー、 不動産業、 造園業、 環境ビジネス関連、 NPO、 NGO、 官公庁など多種多様な業種が期待されます。また、本学の大学院および国公立の大学院への進学も考えられます。